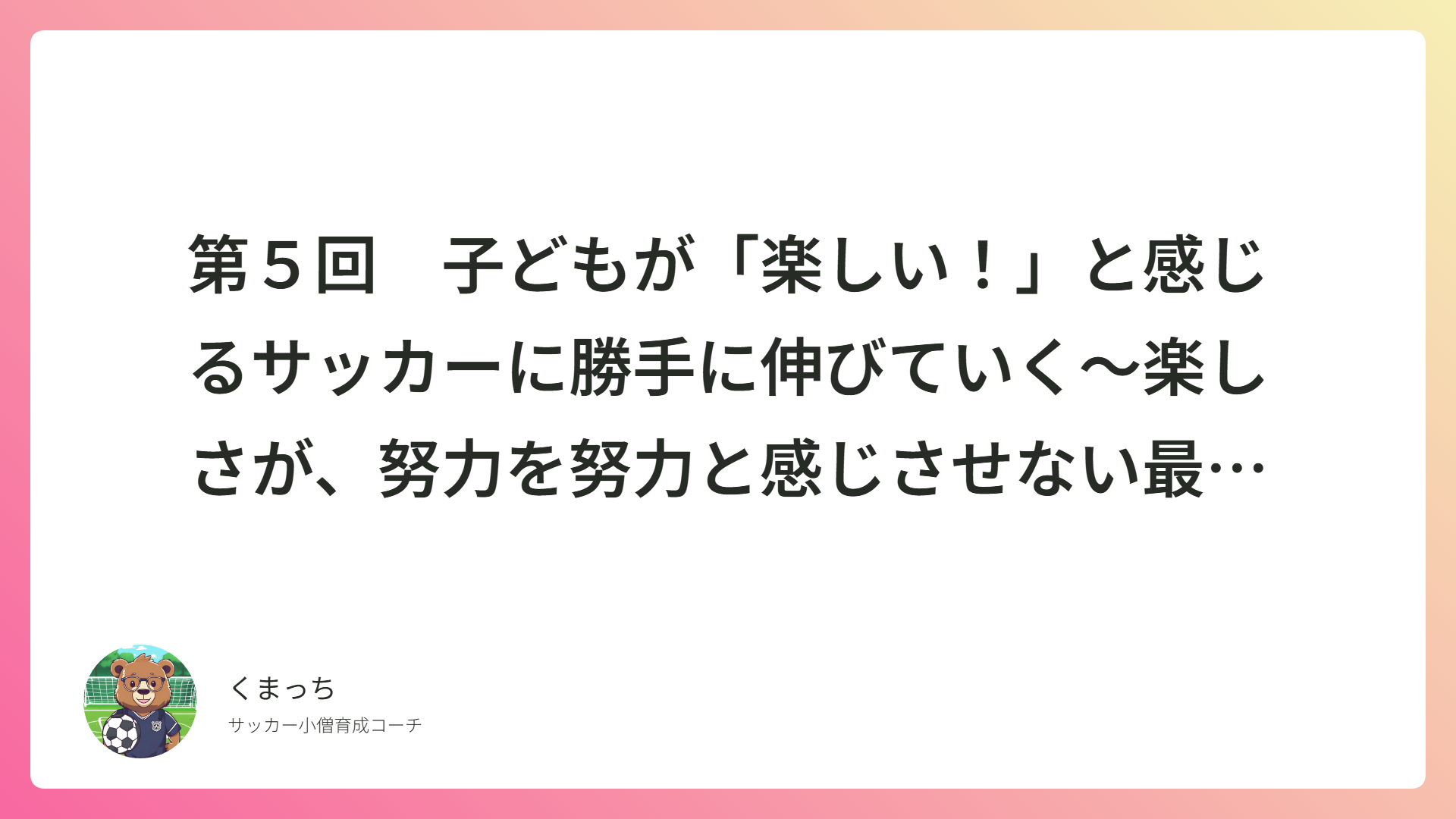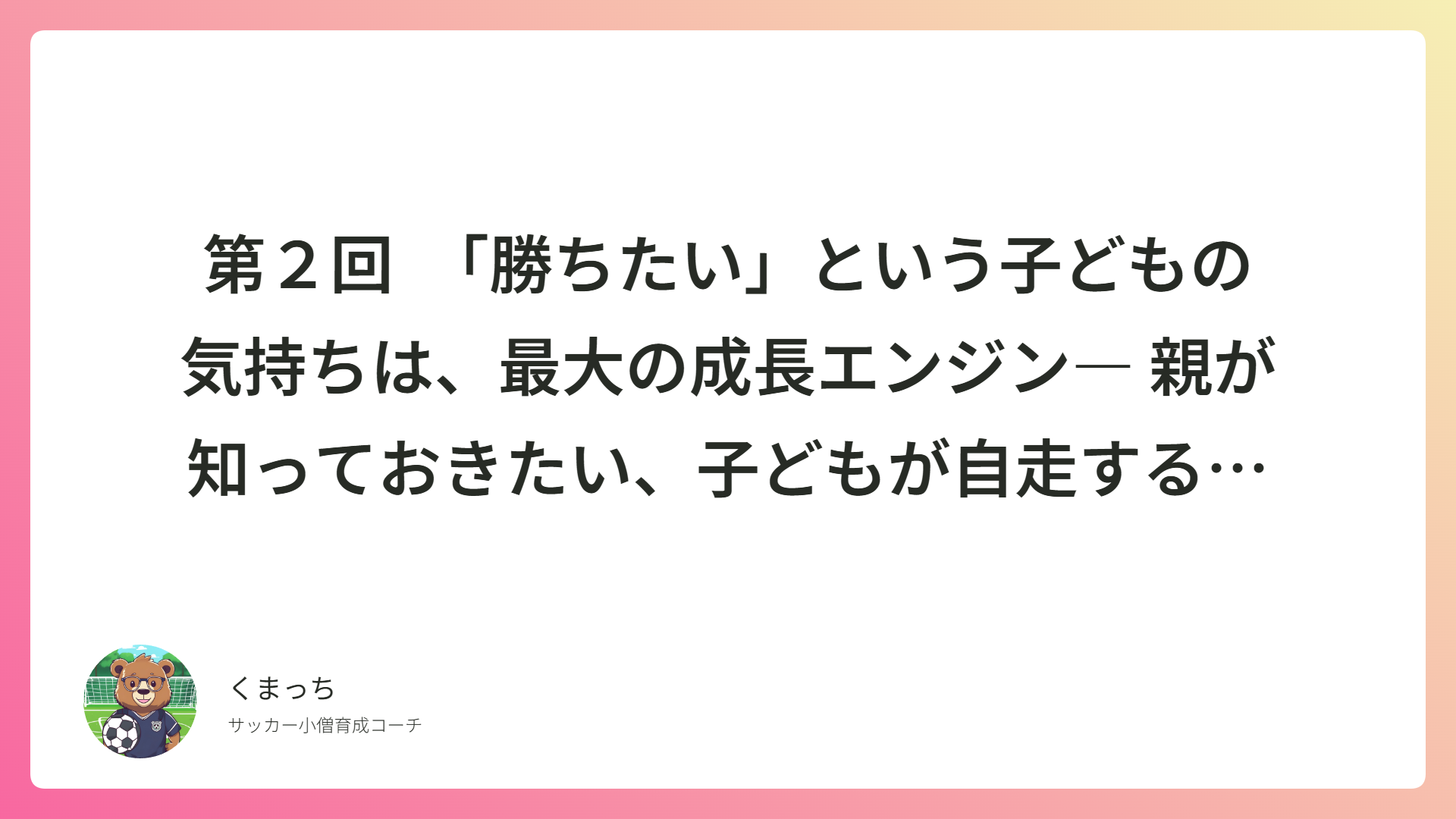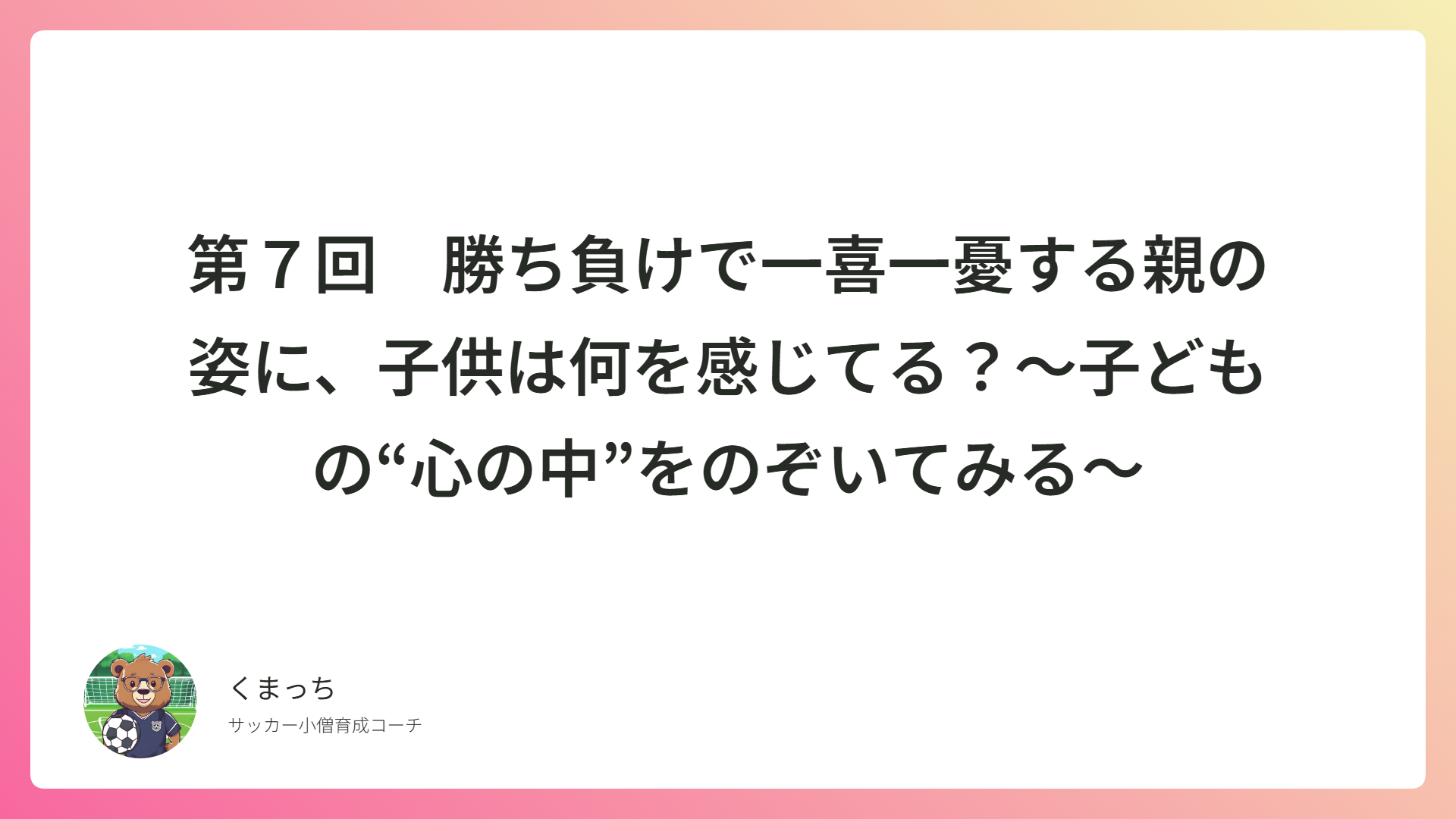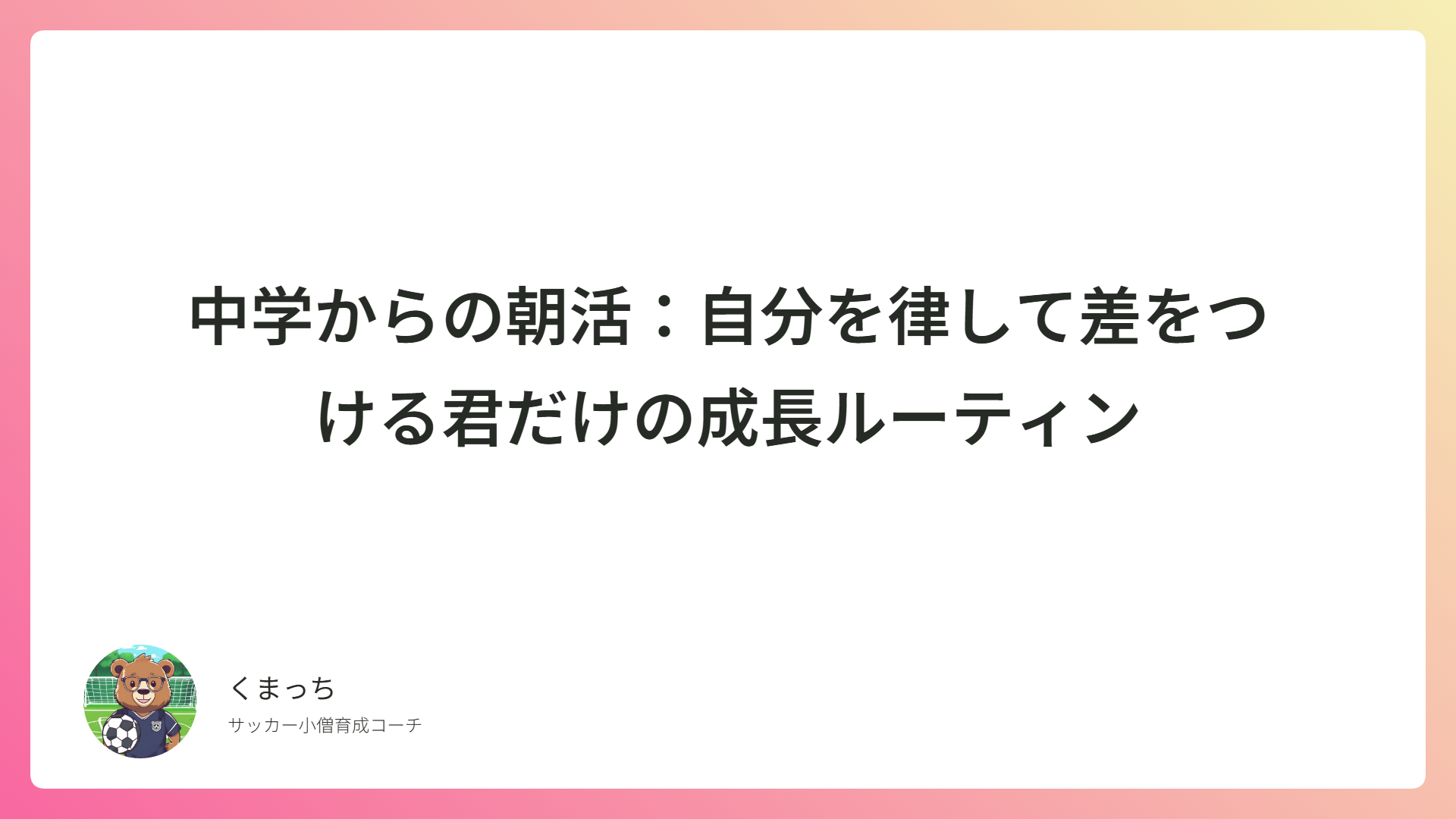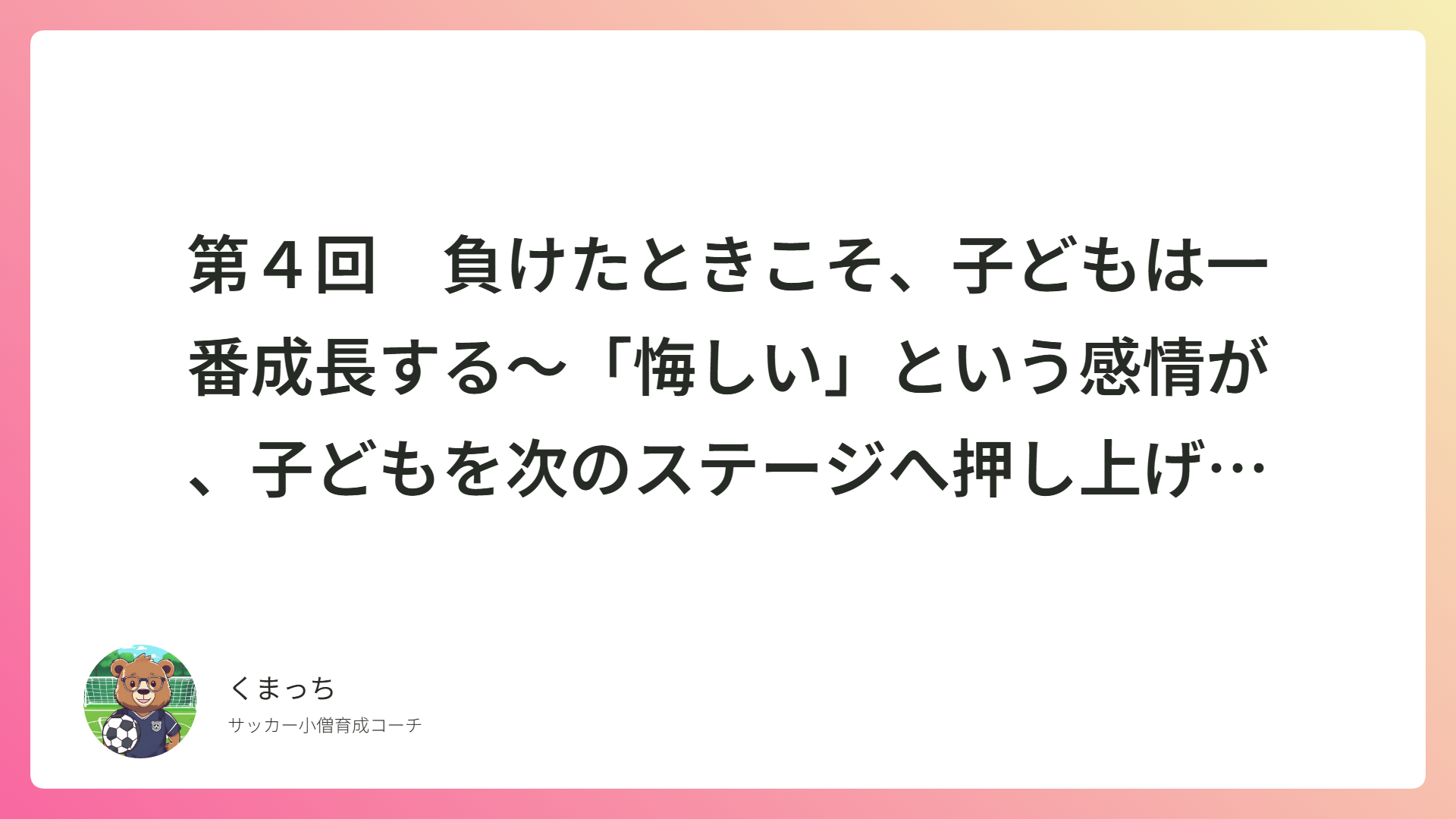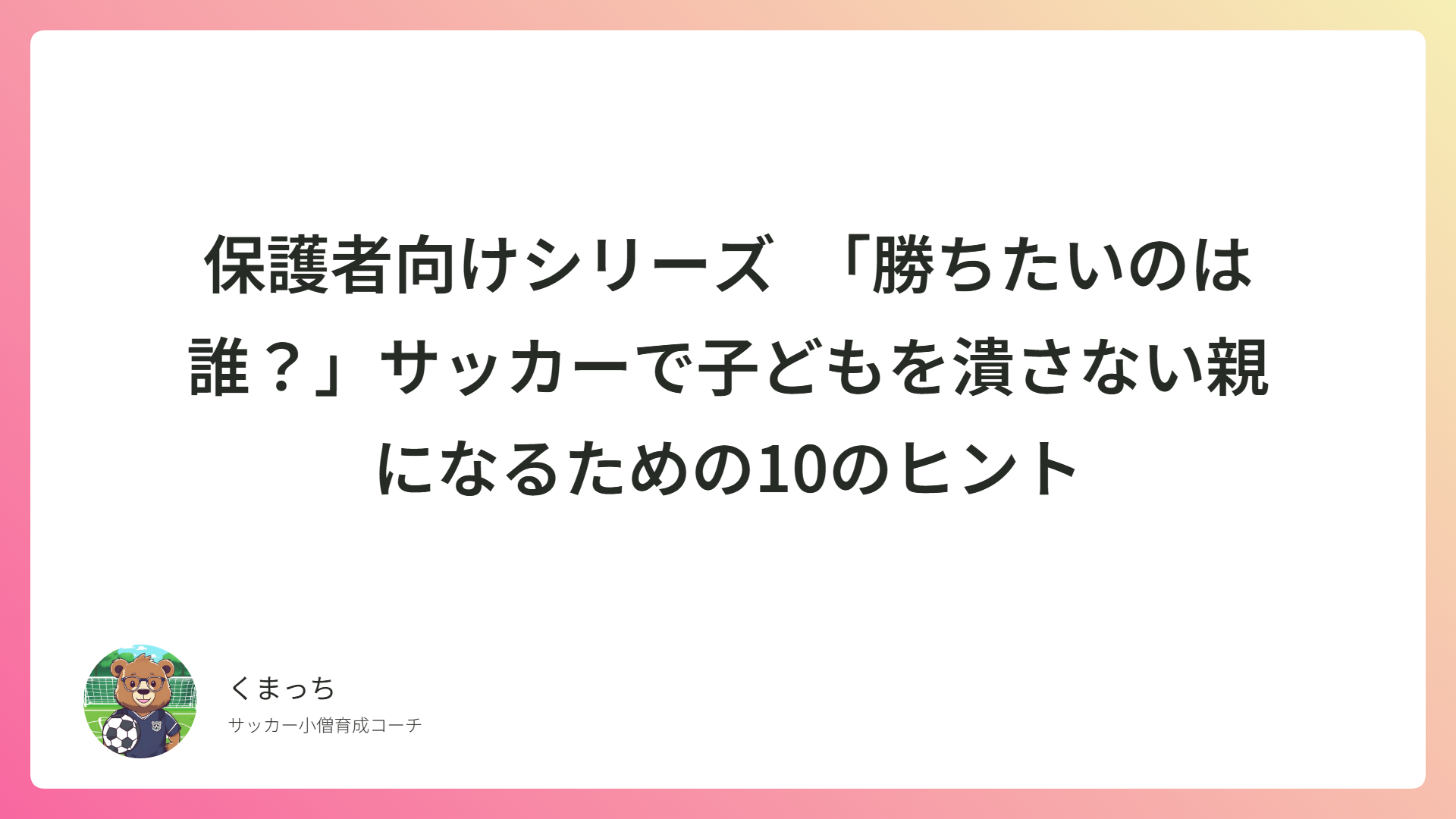第1回 子どもは勝ちたい、大人は育てたい。ズレが生む違和感とは?
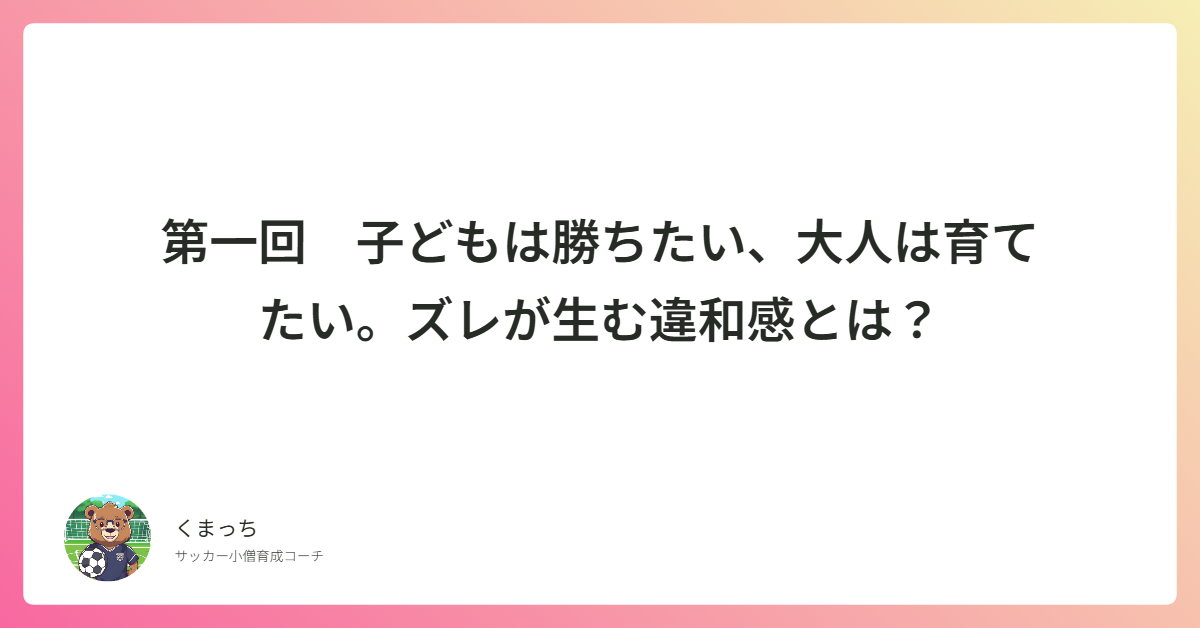
はじめに
サッカーの試合を観ていると、子どもたちの目は真剣そのもの。
「絶対に勝ちたい!」という思いがプレーに表れます。
一方、指導者としては、将来のために「成長してほしい」「技術を身につけてほしい」と考えます。
この“勝ちたい子ども”と“育てたい大人”の間にある温度差が、時としてチーム内の不和や親子のすれ違いを生むこともあるのです。
子どもは純粋に「勝ちたい」だけ
特に小学生年代の子どもたちは、「勝つ」ことがシンプルな喜びであり、モチベーションの大きな源です。
勝てば嬉しいし、負ければ悔しい。それがあるから次に頑張れる。とても自然な感情です。
子どもにとって“勝つこと”は、評価でも戦略でもなく「自分を認めたい」「もっと上手くなりたい」という内なる欲求に直結しています。
大人は“勝ち”をどう捉えているか
保護者の多くは、「我が子に活躍してほしい」「試合に勝って喜びたい」「負けて悔しがってほしい」と願うあまり、試合結果に過剰に反応してしまうことがあります。
ですが、長期的に子どもを育てていこうと考える指導者にとっては、
勝ち負けよりも「学べたか」「チャレンジできたか」「成長に繋がる内容だったか」が重要になります。
ここに温度差が生まれます。
ズレがもたらす“違和感”
例えば、試合に勝ったのに指導者が満足そうでない。
「なんで喜んでくれないの?」「俺たち、がんばったのに」という子どもたちの不満が出ることもあります。
逆に負けたけれども内容的にはチャレンジできていた場合に、「惜しかったね、でもナイスプレーだったよ!」と伝えたときに
「負けたのに褒めるなんて変じゃない?」と戸惑う保護者もいます。
このように、大人側の視点が子どもたちの気持ちとズレてしまうと、
サッカーの場が「楽しい」ではなく「評価される」場になり、無意識のうちに子どもを苦しめてしまうことがあります。
子どもの“勝ちたい”を大切にする
子どもの「勝ちたい」は、育成において極めて重要な感情です。
この気持ちを否定せず、ただ大人がそれに“乗っかりすぎない”ことがポイントです。
子どもが頑張る姿を見守り、時には一緒に喜び、時にはそっと背中を押す。
結果に一喜一憂せず、「どんな経験ができたか?」に目を向ける姿勢が、長期的な成長に繋がります。
まとめ:ズレを埋めるには「信じて見守る」姿勢がカギ
「勝ちたい」という子どもの気持ちに共感しながらも、
親や指導者は「長く続けてよかった」と思える育成を意識して関わることが大切です。
子どもは子どものスピードで、自分なりにサッカーと向き合っています。
焦らず、結果に振り回されずに、“見守る勇気”を持つこと。
それが、子どもと大人が同じ方向を向いて歩んでいく第一歩になるのではないでしょうか。
▶ 次回予告(第2回)
「勝ちたい」という子どもの気持ちは、最大の成長エンジン
子どもたちの「勝ちたい」をどう活かす?
その感情が育む“内発的なやる気”と、大人ができるサポート方法を考えます。